
 | Name | 怪盗レッド・ミラーの伝説 (III) |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 怪盗レッド・ミラーの伝説 | |
| Rarity | ||
| Description | ナド・クライで流行している娯楽書籍。いずれも同じシリーズのものではなく、様々な作者によって書かれた、レッド・ミラーにまつわる安価な小説。物語の真実味は、その紙の品質とほぼ同じ。 |
| Table of Content |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Item Story
| ジーマについて、私たちはほとんど何も知らない。彼はスネージナヤという、飽くことを知らぬ雪に一年中覆われる国の出身だ。その名は、いかなる航海日誌にも、英雄譚にも記されていない。ただ一片の雪のように、ひとつの伝説の表面に舞い落ちると、すぐに溶け、跡すらも残さなかったのである。 彼の故郷は、スネージナヤ・グラードの南東、雪山の影にひっそり佇む小さな町であった。町人は氷の採取を生業とし、雪山の伝承や物語は、氷層の奥に封じられた古代の空気のように、風雪の夜ごとに吐き出される。そこには道に迷った旅人の靴を盗むという、狡猾な霜精の話や、「スネグーラチカ」と呼ばれる蒼白で憂いを帯びた精霊の話があった。スネグーラチカの中には、人間の愛を求め、氷の風の中を彷徨う者がいるという。だが、その愛が裏切られると、恋人の体温をすべて奪い、霜に覆われた、生き写しの彫像に変えてしまうそうだ。ジーマの仲間の一人もまた、スネグーラチカに恋をして山で凍死した。発見されたとき、彼の顔には陶酔にも似た微笑みが残っていた。ジーマはその笑みを見て、「なんてつまらない死に方だ」と思った。彼の胸を満たしていたのは、冒険への渇望だった。誰も経験したことのない、自分だけの運命を欲していたのである。彼は単調な繰り返しを嫌った——奇怪な死に方も、それが繰り返されてきたものであれば忌避した。こうして彼は永遠の白を離れ、南へ——青い海に抱かれた群島へと向かった。そこで耳にしたのが、伝説の怪盗の物語だった。 その頃すでに、レッド・ミラーの名はナド・クライに轟いていた。彼はかつて総督に捕らえられ、スネージナヤ・グラードで公開絞首刑に処されるはずだった。だが、人々がその揺れる死体と共に物語の終わりを確信したその時、総督邸の宝物庫は空となり、壁には黄金の粉で書かれた嘲笑の一文だけが残されていた。誰ひとり、彼がいかにして死の縄を逃れたのかを知らない。この奇跡の復活は、酒場で永遠に語り継がれる逸話となり、港の若者たちの憧れとなった。そして怪盗が再び本業へと舞い戻り、三本のマストを持つ帆船を買い、港で富と刺激を求める船員を募ったとき——ジーマは迷わず手を挙げた。 しかし、船上の日々は伝説のようにはいかなかった。レッド・ミラーは「富める者から奪い、貧しき者に与える」と謳われながらも、その行動は香辛料を扱う商人のように慎重だった。彼の海図には暗礁や海流のほか、「海獣の目撃が伝わる海域」や「海蛇が出没すると言われる霧の海」が赤インクで囲まれており、彼はそれらを避けるために日数を費やして遠回りした。日々の暮らしは、甲板磨き、帆の修繕、壊血病で腫れた歯茎の痛みに耐えることで埋め尽くされた。ジーマは、故郷で感じたものと変わらぬ退屈を覚えた。夜、漆黒の海に向かってこう祈った——真の嵐を、あるいは伝説の海獣を、この目で見たいと。英雄譚のように、怪盗が槍で海獣の眼を貫く姿を、自らの魂を震わせる光景を、彼は見たかったのだ。 その祈りは、望まぬ歪んだ形で叶えられた。船が凪いだ蒼の海域に差しかかったとき、どこからともなく歌声が響いた。それは人の声ではなかった。旋律を持たず、それでいて酔った水夫の魂を直に掴み取る響きだった。風を失った帆は垂れ下がり、船はたちまち動きを止める。やがて、すぐ近くの海面に蒼白で美しい女性の顔が浮かび、「ここを通るなら供物を差し出せ。さもなくば船ごと海底へ沈める」と彼らに告げた。 しかし、レッド・ミラーはその要求を拒んだ。乗員全員に蜜蝋で耳を塞がせ、歌の魅了を防ごうとする。だが、効き目はなかった。伝説の前では俗世の理屈など無力であり、致死の歌に囚われた水夫たちは恐慌に陥った。彼らは総督邸から奪ったモラの箱を次々と海へ放り投げ、「これで通してくれ」と言わんばかりに金色の円盤を紺色の海の底へと沈めていく。だがセイレーンは、人間の富の象徴など意にも介さない。彼女の飢えた視線は、水夫たち一人ひとりに注がれていた。 かつて絞首刑の縄から逃げおおせた怪盗も、そのときばかりは屈せざるを得なかった。レッド・ミラーの刃が、冷たくジーマを指す。しかし、ジーマは抗わなかった。これこそが、故郷を離れ、求め続けてきた彼にとっての「唯一無二」の瞬間だったからだ。冷たい海水が頭を覆う刹那、彼の脳裏に氷像となった友の顔が浮かぶ。スネグーラチカの接吻で凍りつき、陶酔の笑みを見せたまま息絶えたその姿が。彼は「繰り返し」を忌避し、生涯をかけて既知の結末から逃れようとした。だが最期の瞬間、すべての逃避行は、鏡の向こう側に映る同じ結末へと繋がるのだと知る。その冒険は、新たな物語を生むことなく、古い物語の誰も気に留めぬ脚注となって終わった。 |
Obtained From
Shop
| Name |
| n/a |
| items per Page |
|

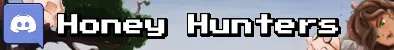



Regarding the alternative for Bennet. Xiangiling might be better. Swirl doesn´t scale with ATK and ...