
 | Name | 怪盗レッド・ミラーの伝説 (II) |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 怪盗レッド・ミラーの伝説 | |
| Rarity | ||
| Description | ナド・クライで流行している娯楽書籍。いずれも同じシリーズのものではなく、様々な作者によって書かれた、レッド・ミラーにまつわる安価な小説。物語の真実味は、その紙の品質とほぼ同じ。 |
| Table of Content |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Item Story
| 恋など信じない令嬢が一目惚れした相手とは? (ナド・クライで人気の娯楽小説。怪盗レッド・ミラーと、総督の娘レオニータ・プロホロヴナ・トルベツカヤ嬢が初めて出会った時の恋物語。本作はすべてフィクションであり、実在の人物・団体・事件とは一切関係ありません) レオニータ・プロホロヴナ・トルベツカヤ嬢こと、ナド・クライ総督の愛娘は、侍女を連れて食堂へ向かっていた。胸の中では焦燥が渦巻いていたが、その足取りはあくまで優雅である。令嬢たる者、振る舞いに乱れがあってはならないからだ。 今朝の新聞を、彼女は誰よりも気にしていた。推測が正しければ、今日は怪盗レッド・ミラーの予告状が掲載される日。なぜそう言えるのか——神出鬼没の渡り烏の行動パターンを、ほんの少しとはいえ掴みかけているからである。父の部下が怪盗の影も形も捉えられずにいることを思うと、自然と言葉が漏れる。「ふん、必ず捕まえてみせますわ!」 父の新聞を読む時間が、今日に限って妙に長い。レオニータはトーストを呑み込み、さりげなく尋ねた。 「お父さま、何かニュースでも?」 「ふむ…お前が心を煩わせる必要はない」トルベツコイ公は新聞を置き、娘に微笑むと、側の赤髪の従者に命じた。「宝飾師を通せ」 すぐに、宝石箱を抱えた人物が恭しく入ってくる。公はちらりとそちらに目をやり、娘に箱を差し出すよう促した。その瞬間、レオニータの顔に一瞬驚きが走る。「どうだ、私が誕生日を忘れたと思ったか?三日後の舞踏会、お前はスネージナヤ——いや、テイワット全土で最も輝く娘になる。さあ、それをつけてみてごらん」 令嬢は素直に箱から首飾りを取り出し、首にかけた。父の選ぶ品は間違いない。デザインもカットもフォンテーヌ製、中央の宝石はナタ産の最高級品すら凌ぐ輝きだ。「少し早いが、父として誰よりも先に言わせてもらおう——愛しい娘よ、誕生日おめでとう」そう告げた公は、首飾りを一瞥した後に真顔になった。 「舞踏会では必ずそれを着けるんだ。重要な客人がいらっしゃるから、その方に会ってもらいたい」 その口調から彼女も察しがついた。この誕生日を機に、貴族令嬢としての婚約が待っているのだと。総督家の娘の縁談に本人の意思が介在する余地などない。相手はスネージナヤの有力者の子息と決まっている。だから、レオニータは恋など信じていなかった。信じても、何の意味もないからだ。父が彼女を溺愛する理由は、その聡明さと美貌ゆえ。だがそれ以上に、養女でありながら従順で慎み深く、理想の「娘」の姿を完璧に体現しているからであった。 ただ、それも数多ある理由のうちの一つにすぎない。 「分かりました、お父さま」と彼女は答える。公は満足げに頭を撫でると、父の笑みを消し、恐れられる総督の顔に戻って執務へと向かった。 父の背中を見送った後、レオニータの胸の奥には、小さな穴がぽっかりと開いたような感覚が広がる。だがすぐ息を整え、気持ちを切り替えると、テーブルの朝刊に手を伸ばした——予想通り、一面には黒い羽根を添えた予告状があった。 総督閣下へ 三日後の月なき夜、貴殿の至宝は我が手に渡る。 寛大なるご厚意に感謝を込めて—— レッド・ミラー ==================== 「どうですか?見分けられそうですか?」 フォンテーヌから来た宝飾師は、更衣室から出てきた二人の赤髪の従者を見て目を丸くした。もちろん、総督邸に仕える本物の従者は一人だけだ。 「左…う、待った…右?違う、ええと…左、いや右だ!うん…右!」 「まさか勘ですか…?」右側の従者が不満げに呟く。 「自信はあるんですか?もし間違えたら、今夜は酷い目に遭いますよ?」と、左側の従者が煽る。 「右だ!」宝飾師はそう言い切るも、額には汗が滲んでいた。 すると右側の従者が「ぷっ」と吹き出し、隣の従者の背中を押して一歩進ませた。「残念、正解はこっち。こいつがお前の想い人だ」 「まったく、本当に分からないなんて!」 「え、いや…右が偽物って言おうとしたんだ!」 「…ふーん」 「ははは、まあまあ。俺たちの目的は『見分けがつかない』ことだろ?思い人でさえ区別するのが難しいなら、今夜の潜入は楽勝だ」と、従者に扮したレッド・ミラーが笑ってその場を収めた。 「一人で本当に大丈夫ですか?もし何かあっても、援護できる人が誰もいないのですよ…」と、本物の従者が心配そうに言う。 「これ以上、仲間を失いたくないんだ」レッド・ミラーは笑みを引っ込めた。「それに、一番危険な仕事——総督邸に潜り込むという仕事はもうお前がやってくれた。あとは安心してフォンテーヌへ戻れ。あそこにも、宝盗団の助けを必要としている人たちがいる」 従者と宝飾師は顔を見合わせてから、一斉にレッド・ミラーに向かって真剣に誓う。「我らはこの世のすべての悲しみを、必ず盗み去ってみせる!」 二人の背を見送ったレッド・ミラーは、夕陽に染まる総督邸へと歩を進めた。トルベツコイ公が宝盗団の弾圧で常に優位に立てるのは、その底知れぬ財力ゆえだ。世界一の怪盗でさえ、そのほとんど無限に等しい財力の前では手をこまねくしかない。財は精鋭を呼び寄せ、最上の武具を揃え、熟練の策士を雇う。そればかりか、法をも黙らせ、あらゆる反抗の芽を黄金の砂に埋めることすらできる。 誰も、その財の限界を知らない。そして何より皮肉なのは——その財がどこから来たのか、本気で問える者が一人もいないことだ。レッド・ミラーはふっと笑う。今や自分は、その答えを知っている——「サンポ・ミル」、持ち主に無尽の富をもたらすという奇物は、総督邸の中にある。その真実に辿り着けたのも、赤髪の従者の調査と宝飾師の鑑識眼、そして間もなく誕生日を迎える令嬢のおかげだ。 ==================== レッド・ミラーの予告状を掲載した新聞は瞬く間に完売した。それから数日間、ナド・クライ全土がトルベツコイ公の娘、レオニータの誕生日パーティーへの期待に包まれる——もちろん、その期待の多くはレオニータ本人に向けられたものではなく、やがて訪れる「怪盗と総督の直接対決」に対してであった。 こうして、総督邸はやむを得ず厳戒態勢を敷き、来賓ひとりひとりの素性を何度も洗うことになった。なにせあの怪盗は、変装の名人なのだ。スネージナヤから招かれた高貴な客人の中には、前日から宮殿内の客間に滞在する者も多い。レオニータは、来客の名前と爵位が並んだ長いリストに目を通す——男爵、伯爵家の嫡子、宮廷の新星、女皇陛下に重用される家系…彼女の首にかけられたネックレスが、なぜか急に鎖のように重く感じられた。 休憩を挟もうと、彼女は庭へ出ることにした。 「お母さん、あの人が総督のお嬢様なの?」 「そうよ」 「でも…どうして人間なの?だって、総督閣下は人間じゃないよね?」 「彼女は総督の養女なの」 「ヘンなの。偉いトルベツコイ公が、どうして人間を養女にしたの…?」 見知らぬ淑女が、少し離れた廊下で子供とひそひそ話をしている。レオニータがこちらを見つめているのに気づき、子供を連れて去っていった。 本当にそうだ。偉いトルベツコイ公が、どうして人間を養女にしたんだろう? 「本当にそうだ!偉いトルベツコイ公が、どうして人間を養女にしたんだろう?」 自分の心の中を、そのままなぞったかのような声が聞こえた。レオニータは思わず辺りを見回す。しかし、庭には彼女しかいない。今のは幻聴だろうか?小さく息を吐き、総督邸の奥にある密室へと向かう。また治療の時間だ…それは毎回、彼女の体力を容赦なく奪い去る。でも幼い頃から、決して弱音を吐かなかった——父を辱めることだけは、絶対にあってはならないから。 なぜか、レオニータの心の中に先ほどの声が蘇った。 それは不思議なほどに温かい声だった。冬の焚き火のように鮮烈で、白雪を溶かすぬくもりを持っていた。 ==================== 夜が更け、舞踏会の招待客が次々と到着した。レオニータの胸も、高鳴りを抑えきれずにいる——ひっきりなしにダンスの誘いに来る人たちの名を、一人として覚えられそうにない。 「10、9、8…」——0時が近づくにつれ、周囲の視線が彼女に集まっていく。先ほどから父の隣に立つ「宮廷の新星」とやらが、まるで彼女の首飾りを射抜くように見つめているのが分かる。「6、5、4…」レオニータは自分でも何を待ち望んでいるかが分からなかった——誕生日?それとも別の何か? 「…3、2——」 その瞬間、会場にいる人々の輪郭が、銀白の泡に包まれたかのように霞み始める。それは徐々に濃くなっていった。レオニータの身体からも時折、こうした白い輝きが溢れ出る。父はそれを一種の病気であり、継続的な治療をしなければ治らない、人間ゆえの欠陥だと言っていた。 「…1!」首にかけていた宝石が、カランと音を立てて床に落ちた。 一瞬にして世界は銀白に染まり、雪深い夜のような静寂に包まれた。心臓は光に呼応するように脈打ち、見えない糸にそっと引き寄せられる。逃げるべきだと頭では分かっているのに、足は優しく押さえ込まれたかのように動かない。これは何?魔法?運命?それとも、これまで信じたことのない、ひとたび踏み込めば燃え上がる、あの感情?時が止まったかのようになり、周理の人々がすべて掻き消える。温かな赤色が彼女へとまっすぐ駆けてきた。 「お嬢様、ここは危険です!総督閣下のご命令を受けて馳せ参じました、私についてきてください!」 「お父さまがそんな命令を…?いいえ、違いますわ。貴方は…レッド・ミラー!」 「緊急事態です。総督閣下からのご命令で——」 「高名な大泥棒と聞いておりましたけれど、いざ目にしてみれば、ただの厚かましい大嘘つきのようですわね!」 「…なるほど、これは賢いお嬢様だ」 「ふん、お父さまはハエ一匹通さない警備体制を敷いていますわ。どう足掻いても逃げられませんわよ」 「その警備の本丸は、密室にあるサンポ・ミルだろう?」 「……!」 「予告状にも書いたはずだ——今夜、貴殿の『至宝』は我が手に渡る。サンポ・ミルは確かに素晴らしいが、『至宝』には遠く及ばない」 「それって、つまり…わ、私を盗むつもり?」 「そうさ。賢くて、愛らしいお嬢様」 「ふん、私はプロホル・トルベツコイ公の娘。貴方はお父さまの最大の敵と言っても過言ではありません。そんな敵にそう易々とさらわれるつもりなんてありませんわ!」 「お前は本当に彼の娘か?高貴なる公が、なぜ人間を養女にする…?」 「……」 銀白の力、治療、サンポ・ミル、公の尽きぬ財力、そして「養女」。瞬時に、すべてが一本の線で結ばれた。そうか、自分こそが父の財力の源。「治療」と称された儀式は、サンポ・ミルに無数の宝石を複製させるためのもの。いや、本当は最初から気づいていた。ただ、ずっとその事実から目を背けていただけで… 「おっと、あやうく忘れるところだった。ギリギリのタイミングでダイヤに仕込んだ細工を起動したからな——まあ、間に合ったから良しとしよう」赤髪の従者という変装を解き、本来の姿を現したレッド・ミラーが、彼女の耳元でささやく。 「ハッピーバースデイ!」 その後の顛末は、誰もが知っている。レッド・ミラーは総督邸の秘宝を根こそぎ奪い去り、レオニータは彼の顔を見た瞬間、一目で恋に落ちた。そして、貴族としての誇りをすべて捨て、彼と共に放浪の旅に出た。レッド・ミラーの伝説など後世の作り話に過ぎないと言う者もいるが、それは恋を知らぬ者が「恋など存在しない」と言うのと同じこと。ただ、自分がその瞬間を経験したことがないだけなのだ。 |
Obtained From
Shop
| Name |
| n/a |
| items per Page |
|

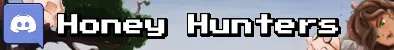



Regarding the alternative for Bennet. Xiangiling might be better. Swirl doesn´t scale with ATK and ...