
 | Name | 怪盗レッド・ミラーの伝説 (I) |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 怪盗レッド・ミラーの伝説 | |
| Rarity | ||
| Description | ナド・クライで流行している娯楽書籍。いずれも同じシリーズのものではなく、様々な作者によって書かれた、レッド・ミラーにまつわる安価な小説。物語の真実味は、その紙の品質とほぼ同じ。 |
| Table of Content |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Item Story
| 10モラ・奇譚ミステリー全集!怪盗レッド・ミラーとサンポ・ミル(季刊特装合本版) (ナシャタウンで出回っている安物の娯楽小説。一冊わずか10モラで買える。本来は怪盗レッド・ミラーが総督邸から霜月の至宝である「サンポ・ミル」を盗み出す過程が描かれるはずだった。ところが実際は、読者を惹きつけるためなのか、彼を巡って様々な美女たちが火花を散らすシーンで埋め尽くされている。) …… 第四章 鷹よりも危険な美女!「セキレイ」登場!月明りの中、怪盗レッド・ミラーに近づくその目的とは…! 「まあ、可愛いお嬢さんたちを放って、こんな所まで一人で夜景を楽しみに来るなんて——あなたって本当に冷たい男ねぇ、ダーリン」 その声は璃月の極上の絹のように柔らかで滑らかだが、わずかながらスメールのバラの棘にも似た猛毒が潜んでいる。しかし、レッド・ミラーは振り返らない。あまりにも聞き慣れた声だからだ。 次の瞬間、猫のようにしなやかな身のこなしで、一人の女が彼の傍らに舞い降りた。年の頃は二十代といったところだろうか。淡いバイオレットの長い髪が、わざとらしく露わにしている白い肩と首筋にさらりと流れ落ちる。月光を凝らしたかのような銀色のイブニングドレスが、彼女のしなやかな肢体を際立たせる。だが、何よりも目を奪うのは、小悪魔を思わせる茶色がかった赤の瞳だ。 これが「セキレイ」——あるいは、レッド・ミラーのように、彼女に近づくことを許された数少ない者たちが、時に「A」と呼ぶ女。ナド・クライ随一の盗みの腕を誇り、その悪名において怪盗と肩を並べる、蛇蝎のごとき美女。彼女が欲しいと思った物は、どんなに貴重なお宝でも、必ずその手に落ちる。だが飽きるのも早く、気まぐれに街の貧民にくれてやり、時には海へと投げ捨てる。社交界では数多の男が競って彼女に尽くすが、当の本人は男たちの心を弄ぶばかりで、応えたことは一度もない。 そんな悪女が唯一手に入れられなかったもの——それが、怪盗レッド・ミラーの心だった。だからこそ彼女は、この端正で謎めいた男に執着し、あらゆる手を使って、その心を自分だけのものにしようとしている。 「高級な香水と、安っぽい野心の匂いがするな、セキレイ」 彼女は笑い、怪盗の隣に当然のように腰を下ろす。二人の距離は、触れそうで触れないほど近いものだった。 「どうしたの?他の男が贈ってくれた香水に嫉妬でもしたのかしら?」絹の手袋に包まれた細い指が、彼の右腕をゆっくりと撫で下ろす。「でも私の鼻に届くのは、過剰な自信の匂い。レッド、あなたの狙いはサンポ・ミル——あまりにも分かりやす過ぎるわ。違うかしら、ダーリン?」 「その通りだ。『霜月の子』から奪われた『サンポ・ミル』、それから他の不義の財も、総督閣下にはまとめて返してもらう」レッド・ミラーがまっすぐ視線を合わせた瞬間、彼女の心臓が一瞬だけ高鳴る。白い頬に朱が差すが、それを隠すように軽薄で挑発的な笑みを浮かべる。「ここは今宵、俺の舞台だ。悪いが、お前には他を当たってもらう」 「それは違うわ」彼女は身を寄せ、唇が触れそうな距離でささやく。「この舞台は十分大きいもの、二人くらい余裕で立てる。でも、スポットライトを浴びるのは一人だけ。サンポ・ミルは私が先にいただくわ、ダーリン…その後は、そうね、あなたが私を楽しませてくれたら、遠くから眺めさせてあげてもいいわ」 キンッ! 言葉が終わるや否や、彼女は稲妻のような速さで細身の短剣を抜いた。しかし、怪盗はとうに慣れきっている。彼女が好むのは、こうした意味のない、危うげで唐突な、必ず彼に防がれる攻撃だ。彼もまた腕を軽く上げ、籠手で刃を弾く。鋼と鋼が一瞬、鋭くぶつかり合った。 「相変わらず好き勝手してくれるな。いずれ痛い目を見るぞ、セキレイ」 「ふふ、好き勝手できるのは美女の特権よ。気に入らないなら、あなたの手でお仕置きでもしてみたら?ダーリン」 月下を渡るそよ風のように、彼女は二歩引き、軽やかな投げキッスを残して塔の下の闇へと消えた。ただ、香水の匂いだけが冷えた夜の空気に漂っていた。 (間の章は破り取られている。おそらく別の用途に使われたのだろう…) 第十七章 総督がサンポ・ミルを盗まれたことに激昂しているその時、突然、スネージナヤから来たという刑事たちが雪崩れ込み、彼を縄で縛り上げた!まさか…! 「ハハッ、総督閣下。どうやら怒りで冷静さを失っているようだ。あの怪盗レッド・ミラーがどんな男か忘れたのか?あの『憎たらしい』泥棒は、もともと変装の達人だ。男女老若、どんなやつだろうと本物そっくりに演じてしまう——そうだろ?」 「お、お前——そんな馬鹿な!もしお前がレオンノフ警部のなりすましだというなら、特務隊がとっくに…」 「レオンノフ警部」と呼ばれた男は高らかに笑い、縛られた総督を嘲笑うかのように、彼の周りを二周、ゆっくりと回る。 「特務隊?それはお前を縛り、宮殿の出入りを封じている連中のことか?あれは俺の部下だ。特務隊のふりをさせたら、お前の部下は疑いもしなかった。知らないのか?スネージナヤの兵士は、上官——たとえそれが『上官になりすました者』でも、その命令には無条件に従うものだ。今ごろ『霜月の子』の秘宝は無事に聖女の手に戻っている。陛下のご意思に背き、霜月の子に宣戦布告をする覚悟でもない限り、お前がサンポ・ミルを取り戻すことは不可能だ」 「貴様…呪われろ、この泥棒め!サンポ・ミルだけならまだしも、なぜ私のコレクションまで根こそぎ奪った!」 「それがどうした?お前が『自分の物』と言うその財産だが——もとはといえば、この地の貧しい人々から奪ったものだろう?」男の態度は終始エレガントなまま、総督の怒声など意にも介していなかった。「俺たちは俺たちのやり方で自由を守る。なぜなら、俺たちのために戦ってくれる者などいないからだ。一般人から略奪する賊も、高みから見下ろす総督も——俺たちにとっては同じだ。まあ、安心してくれ。財宝はお前の代わりに全部、元の持ち主に返してやった」 その時、部屋の反対側で、警部に扮した「セキレイ」が総督には聞こえない声で呟いた。 「まったく、どうしようもない男…何ひとつ自分の物にはしない、なんて言いながら、結局、霜月の一番大事な宝物をこっそり懐にしまってるじゃないの…」 その言葉に「カゲイタチ」は眉をピクリとさせ、思わず部屋の中央で縛られている養父から意識を逸らしてしまう。 「レッド・ミラーは確かにサンポ・ミルを聖女に渡したはずですわ…まさか、私たちが目を離した隙に、偽物とすり替えた…?」 「ふふ、まだ分からないの?だから若い娘は、この男に騙されるのよ…」彼女はわざとらしくため息をつき、くすりと笑った。「彼が盗んだのは——サンポ・ミルじゃない。霜月の娘の秘められた恋心よ」 |
Obtained From
Shop
| Name |
| n/a |
| items per Page |
|

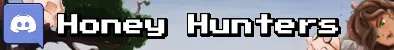



Regarding the alternative for Bennet. Xiangiling might be better. Swirl doesn´t scale with ATK and ...