
 | Name | 秋暮の炎・2 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 秋暮の炎 | |
| Rarity | ||
| Description | 花翼の集で受け継がれているウォーベン。元々は異なる時代の二つの物語だったようだが、いつの間にか一緒になってしまった。 |
| Table of Content |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Item Story
| 「ここは母が生前大好きだったお花畑よ」彼女は優しく答えた。細い指は名前も知らない花を優しくなでているが、声は彼女が倉庫の下に埋めた燃料缶を思わす熱気をはらんでいた。彼女はあえて彼の顔を見なかった。彼はきっと、利口ぶった陳腐な比喩や心に響かない慰めを言うのだから。過ぎ去ったことをいつまでも気にしていても仕方がない、と。自分と共に未来を思い描こう、と説得しようとするだろう。その未来が訪れることなどないとも知らずに。そして彼女の頬を優しくなでるのだ。まるで数えきれないほどの夜、彼女がこの花を愛でたように。秋の夕焼けの残照と四方から響く虫の声に彼女は鬱陶しさを覚えた。彼の話が終わるのを待たず、花を手折り、驚く彼に微笑んで、火のような花を慎重に金糸で織られた彼の襟に留めた。「行きましょう、きっと誰かがここを見てくれるわ。」 龍は少し戸惑いはしたが、鉄のカーテンのような瞼を少し細め、周囲の乾いた暗闇を見渡した。カラッと乾燥した熱い暗闇を推し測った。無論、龍は謀られてなどいない、一瞬たりとも。そう、彼女が自分をここへ誘い込んだのだ。だが、この狭く仄暗い山の洞窟に誘いこんだところで何になる?龍は彼女を、自身が誇りに思う眩しい綿毛を見るような——しかし蔑みのこもった——視線で見下ろした。この女はまったく母親に似ていない。数十年前、私の喉を矢で穿った弓使い、モコモコ駄獣を追い立てるように自分を深い森へ追いやった女、人間の村落を蹂躙するというちょっとした楽しみを奪っていった女——憎むべきあの女にまったく似ていない。いや、このぶるぶると震える幼い生き物は、あの女の弱弱しい残響でしかなく、私の鋭い爪どころか、あの青白く恐ろしい運命にすら抗えないではないか。この女の存在は彼女自身の血筋に対する愚弄であり、龍族の古の血に対する恥辱そのものだ。いったいどんな馬鹿げた考えで私をここに連れてきたのだろう?こんな幼稚なことをしても彼女の死を引き寄せるだけだというのに。その時、空気中にかすかに怪しい匂いが漂い、一抹の不安が頭をよぎった。だが、その不安もすぐに自らの傲慢さにかき消されてしまった。 古くなった木の扉を押し開け、彼は幽かに漂う怪しい匂いを嗅ぎ取った。燃料もしくは薪のような匂いだ。しかし、彼は意にも介さず、彼女の手を引いて倉庫の奥、暗がりへと入っていった。何が起ころうとも必ず彼女を導くのだと、心の中で言い聞かせて。いつか自分は、これと同じように自分は花翼の集を導くのだからと。しかし何の気なしに上を向くと、倉庫の天井に巨大な龍の頭蓋骨が吊るされているのが見えた。彼の記憶では、こんな収蔵品は無かったはず。少なくとも彼が花翼の集を離れるまではなかったのだが、今はそんなことはどうでもよかった。リアンカと彼女が選んだ後継者は皆死んでしまった。彼女のか弱い二女では、部族の権力を維持するにもあまりにも弱すぎる。ここは彼に、小さい頃から二女の傍に寄り添い、聖王から深く信頼されている彼にこそ、無知な人々を聖王の描いた未来へ導く資格があるのだ。エンヤンゴンデホ族親もこれに反対の意を唱えることは無かった。彼もまた花翼の集の子だからだ。新婚初夜が過ぎれば、反対する声もすべて静まるだろう。 静寂の中、見たことのない夢のような奇妙な考えが、ふと彼女の脳裏によぎった。彼女が憧れていた、かつて自分のそばに寄り添ってくれたあの青年が、花翼の集を離れることなく、聖王にも仕えなかったら…彼女の成長を見守り、彼女が従順ではなくなっていく様を見ていたら、彼は喜んだだろうか、それとも失望しただろうか、と。野獣のような、炎のような眼は暗闇の中で彼女をじっと見つめていた。その鼓動と彼女の呼吸が混ざり、境が無くなる。目立たない動きだった。火花が導火線に燃え移り、線を辿って燃料缶に火がついた。 |
Obtained From
Shop
| Name |
| n/a |
| items per Page |
|

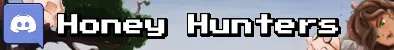



mávuika eu quero ela