
 | Name | 秋暮の炎・1 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 秋暮の炎 | |
| Rarity | ||
| Description | 花翼の集で受け継がれているウォーベン。元々は異なる時代の二つの物語だったようだが、いつの間にか一緒になってしまった。 |
| Table of Content |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Item Story
| 彼らが倉庫へ伸びる曲がりくねった小道を進んでいく。霧雨のようにはらはらと舞い散る落ち葉の雨を通り抜ける彼らを彼女は静かに眺めていた。自らの記憶にある彼の面影と今の彼の姿を重ねようとしたが、数年も見ないうちに彼はすっかり大きくなり、身なりもいくらか豪華になっていた。だが、身なりに関しては想定内だ。彼は今や大同盟の審理官で、聖王の名のもとに花翼の集の旗印を引き継ぎにやってきたのだから。ふさわしい装いに変わっているのも当然のことだ。彼は変わった。だが、彼女は思った——変わらないものなんてない。ただ、鈍いところは昔のままね、と。「あの料理人の作ったものなら、きっと君の口にも合うはずさ。」彼はそう言うと、彼女の返事を期待してか、少し待つようなそぶりを見せた。しかし、彼女が返事をしないのを見て、「僕たちが灰燼の都に着いて、陛下に謁見したら…」と続けた。 耐えがたいほどの長話を、鼓膜をビリビリと震わす龍の鳴き声がさえぎった。龍は彼女から、顔をしかめたくなるあの匂いを嗅ぎ取った。南の泉から湧き出る水でさえ洗い流すことのできない悪臭だ。「卑しい虫けらめ。」龍はそう思った。狂気に侵された者と裏切り者とが巡らせた策でこの灼原を奪い取れるだなどと、うぬぼれた卑しい虫けらどもめ。龍は彼女を砂地に磔にしてやろうと鋭い爪でしつこく追い回す。もう彼女に二度避けられていたが、そんなことに構いもしなかった。 彼女は彼の思いに気づかなかったかのように、微笑みだけ返した。彼は彼女の口角から感情の機微を読み取ろうと、しばらくじっと見つめていたが、感情を読み取りづらい彼女の表情からは拒むような感情も見出せなかった。思えば、彼女はいつもこうだった。慎み深く、従順で、まるで水辺に暮らすか弱いカピバラのようにすべてを運命に委ねていた。心の冷たい彼女の母親とは正反対だ。「心配しなくていい。」彼は言った。「たとえ彼らが全員いなくなっても、私はずっと君のそばにいる。死が私たちを分かつまでね。」彼女はちらりと彼を見て微笑み、素直に差し出された手をとった。「死がふたりを分かつまで。」彼女は自分に言い聞かせるかのように、その言葉を小さく繰り返した。ふとした瞬間、彼女の完璧で美しい表情にヒビが入ることもある。だが、彼がそれに気づいたことはなかった。いや、彼はこれまで何も気づいてこなかったのだ。可哀そうな人——彼女は思った。いつも自分の役割を一生懸命果たそうとしているのに、誰にも褒めてもらえないなんて、なんて不運なのだろうか、と。 しかし運は決定的な要因ではなく、この長い狩りにおける単なる解釈でしかない。ここ数年、彼女はずっとこの巨龍と、その邪悪な気配を追い続けてきた。彼女は龍が見栄っ張りであり、言葉に惑わされることがあると見抜いていた。また、龍は自身を運命を統べる者であり、いずれやって来る終末に抗いうると思い込んでいることも知っていた。すらりと細い彼女の指が張り詰めた弓の弦を引くように、偽りの幻想が必ず龍をここへ連れて来ることも分かっていた。そんな彼女は微動だにせず、近づいてくる獣を見つめていた。獣の巨体はまるで瓶からあふれ出す油のように、洞穴のほとんどを占めていた。彼女は視線——捕食者の視線を感じた。そこでは彼女はちっぽけな虫けらでしかなく、いともたやすく風に吹き飛ばされる羽のような存在だった。「陰湿で悪知恵の働く虫けらめ、ここはどこだ?」 |
Obtained From
Shop
| Name |
| n/a |
| items per Page |
|

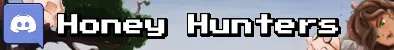



mávuika eu quero ela