
 | Name | 辺境夜話・ヴァルコラク |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, loc_fam_book_family_1071 | |
| Rarity | ||
| Description | スネージナヤに伝わる民間の物語。フェイの知られざる秘話が記されているという。「ヴァルコラク」という名の危険なフェイについて語られている。 |
| Table of Content |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Item Story
| シズボールは狩小屋で二日二晩も見張りを続けていた。日中降り積もった雪が森を覆い、その夜は特別静かだった。狩りの経験豊富な彼でさえ、つい眠気に襲われてしまった。だが村で起きた、首筋を噛み裂かれ血を流し続けていた娘の無残な姿を思い出すと—— 「あの畜生に必ず代償を払わせてやる!」その思いで彼は幾分気を引き締めた。鬱蒼とした森は悪夢が織りなす黒幕のようにも感じる。その時、南東の方角から「サワサワ」という微かな音が聞こえ、巨大な黒い影が素早く近づいてくるのがうっすらと見えた。そしてそれは、瞬く間に目の前まで迫っていた。シズボールは弩を握り締めた。彼のいる場所は視界が悪く、倒れた松の木が自分とその黒い影の間を遮っていた。松葉の隙間越しに、その獣の前足が自分の頭ほどもある大きさだと分かった。漆黒の硬い毛は、闇から生えてきたいばらのようだった。 その怪物は突然足を止めた。気付かれてしまったのか?彼は戦闘態勢のまま全身を緊張させたが、向かってくる猛獣が突然身を翻すとは思わなかった。「シュッ!」反射的に放ったボルトは怪物の右肩に命中したが、それは痛みに振り回されることもなく森の中へと逃げ込んでいった。急所は外したものの、この至近距離なら相当な傷を負わせたはずだ。 シズボールは血の跡を追って進んでいくと、その真っ赤な血痕は深い森の中にある豪華絢爛な屋敷の前で途切れていた。その敷地内の邸宅は、まるで往日の油絵から切り取られ、この陰鬱な森の海に嵌め込まれたかのようだった——高くそびえる尖塔は木々の梢を突き抜け、窓の桟からは微かな冷たい白光が漏れ出し、まるで来客を見つめる目のようだった。「奇妙だな。人里離れた場所に、こんな屋敷があるなんて…」シズボールは不審に思いながら、その古い屋敷の玄関の鈴を鳴らした。 迎えに来たのは身なりの整った老執事で、顔色が少し青白いことを除けば、確かに人間のようだった。シズボールが怪我をした獣のことを尋ねると、老執事は困惑した様子で首を振り、見たことがないと答えた。猟師は血の跡に導かれてここまで来たのだと告げ、その怪物がこの屋敷に潜んでいるかもしれない、見つけ出さなければ全員が危険な目に遭うかもしれないと伝えた。老執事は一瞬考え込んだ後、猟師を自らの主の元へと案内した。そこにいたのは二十歳前後に見える眉目秀麗な少年で、その長い黒髪は腰まで垂れ、繊細で優美な容姿だった。二人の話に静かに耳を傾けていた少年は、頷いてこう言った。 「わざわざこの雪の中を追ってきてくださって…さすが狩人です、獲物を手中に収めるまでは決して諦めないのですね」。狩人の助力への感謝として、館の主は心からの歓待の意を示し、共に夕食を取ることを提案した。外では吹雪が激しさを増していることもあり、館の住人を守るためにも、また怪物を探すためにも、今夜はここに留まるべきだろう。 「黒い髪…」シズボールは不審に思った。彼は幼い頃から霜月の子の拠点で育ち、老司祭から聞いた話によると、数多の妖精の中で最も手に負えないのは「ヴァルコラク」だという。奴らは二つの心臓を持ち、人間と妖精という全く異なる姿に変身できる。しかし、どんな姿に変わろうとも、その毛の色は常に同じであり——あの狼の怪物の体毛と、目の前にいる若い貴族の髪の色もまた、全く同じだった。 シズボールは少し考えた後、主の招待を受けることにした。食事の席で、彼はあらゆる方法で相手を試した——コショウやニンニクといった狼が最も嫌うものを料理に加えたり、身に着けていた月明かりのように淡く輝くお守りを見せても、主は少しも不快そうな様子を見せなかった。若者は優雅にそれらの料理を口にし、さらにはシズボールのお守りを手に取って興味深そうに鑑賞さえした。美味な食事の後、パイプオルガンを奏でてシズボールをもてなしたが、当然猟師が警戒を解くことはなく、音楽に耳を傾ける余裕などなかった。 ようやく就寝の時間となり、若き主が別れを告げようと立ち上がった時、突然猟師の方へ向き直り、意味深長な様子でこう言った。「今夜は月明りがなく、外はまた吹雪が降っています。どうか寝室から出ないでください。例の怪物の件は明朝、一緒に調査しましょう」ふん、そう言うと思っていた。シズボールは心の中で思いながら、自室で外が静まるのを待ち、そっと暗闇の中へ忍び出た——暗夜の潜行こそ、猟師の真骨頂なのだ。 この屋敷は、やはり何かがおかしい。 彼は眠り込んでいる数人の使用人を調べた。彼らの手足には微妙な傷跡があり、深くもなく浅くもなく、命に関わるものではないが仕事で負うような傷とも違っていた。青ざめた執事の顔色を思い出し、彼の不安は募る一方だった。一部のヴァルコラクは、人の生き血を好むという噂を聞いたことがある…さらに彼の背筋を凍らせたのは、パイプオルガンだった。なんと、パイプが骨で作られているのだ!狩人としての経験から見ると、それは普通の野獣や家畜の脛骨ではないようだった…よく調べようとした矢先、廊下の奥の部屋から、かすかな足音が聞こえ、大門へと駆けていくのを感じた。シズボールは影に身を潜め、その後を追った。暴風雪の中、前方の人影がおぼろげに見えた——それはまさしく、若き館の主だった。 猟師は吹雪に逆らいながら一歩ずつ追跡を続けた。二人は前後して森の中の開けた場所へとたどり着き、若者は突然立ち止まった。シズボールは木の陰から顔を覗かせ、様子をうかがった。吹き荒れる雪の中、黒髪の若者がゆっくりと全ての衣服を脱ぎ始め——その右肩には、まだ癒えていない矢傷があった! 突然、若者の周囲の雪——空から降る雪も、地面に積もる雪も全てが宙に浮かんで静止し、地面に隠れていたフロストランプの花々が姿を現した。花から放たれる光が血のように、絶え間なく若者へと集まっていく。錯覚かもしれないが、彼の肩の傷が徐々に癒えていくように見えた。 あの血に飢えた獣だ!シズボールに迷いはなかった。不意打ちは卑怯かもしれないが、人間が妖精を倒すためには、やむを得ない手段だ。短剣を抜き、木陰から飛び出して若者に突きかかる。だが若者は素早く振り返り、シズボールの手首を押さえつけ、短剣は彼自身の胸元を掠めた。二人は地面を転がり、刃先は指先できらめき、息遣いと怒号が入り乱れる中、互いに手に込める力を緩めようとはしなかった。もみ合ううちに、シズボールは次第に力が尽きてくる。まさか!目の前の美しい若者が、純粋な腕力だけで自分を圧倒するなんて——「化け物め!お前は化け物だ!」形勢不利と悟った狩人は絶望的な叫び声をあげた。 「いえ…僕は…僕は怪物なんかじゃ…」 若者の目に一瞬の躊躇いが生じる。今だ!シズボールは素早く短剣を奪い返すと、そのまま相手の胸に突き刺した。鮮血が舞い散る雪の中に飛び散り、若者の瞳の光が次第に曇っていく。猟師が息をつく間もなく、本来死んでいるはずの体から漆黒の毛が不気味に生え始め、若者は巨大な狼の怪物へと変貌した。シズボールは驚愕し、短剣を引き抜いてとどめを刺そうとしたが、巨大な爪が刀身をしっかりと掴み、自らの胸に深々と突き刺したまま固定している。怪物は高笑いをあげ、その声は吹雪の中に不気味に響き渡った。彼は猟師を見つめ、掠れた声で興奮気味に低く唸った。 「僕たちヴァルコラクは、生まれつき2つの心臓を持っている」血が刃の切り口から溢れ出るにもかかわらず、怪物の目はますます輝きを増していった。「余計な心臓を刺し殺してくれたこと、感謝します。今、ついに僕は完全な姿になった!」 その言葉が終わらぬうちに、怪物は冷たい光を放つ牙が並ぶ口を大きく開け、狩人の首筋に噛みついた。 物語はここで途切れている。これが伝説なのか、それとも明らかにされていない真実なのか、誰にも分からない。ヴァルコラクと呼ばれる妖精は本当に二つの心臓を持っているのだろうか?彼らは今ではほぼ絶滅し、多くの人々にとって荒唐無稽な伝説となってしまった。しかし、スネージナヤのエフラニア・オルロワ公爵夫人こそがヴァルコラクだという噂がある。ただし、全身が狼の毛で覆われているわけではないらしい。この伝説の真偽を確かめるのは簡単なことだが…親愛なる読者よ!おそらくあなたにも、あの高貴な夫人にそれを尋ねる勇気はないだろう! |
Obtained From
Shop
| Name |
| n/a |
| items per Page |
|

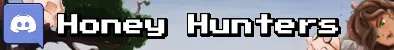



Regarding the alternative for Bennet. Xiangiling might be better. Swirl doesn´t scale with ATK and ...