
 | Name | クントゥルの物語 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, クントゥルの物語 | |
| Rarity | ||
| Description | ナタで口伝えに長く語られてきた民話。最初の作者は不明。 |
Item Story
| クイールが天に戻ってから、太陽の金の矢で目の光を失ったウククは部族に残り、まだ幼いクントゥルを一人で育てることにした。この経緯を部族の者はおおかた知っている。支え合う親子を部族から追い出しはしなかったが、二人は煙たがられていた。寡黙な父のみならず、まだ話せないクントゥルも巻き込まれてしまっていたのだ。なにせ二人が現れれば、必ず太陽は分厚い雲に隠れ、日光が遮られるのだ。彼らと関わりを持とうとした者が太陽の怒りを買わないと、誰が断言できるだろう?そういうわけで、当時の部族の中に疫病神たちに関わろうとするものはいなかった。 太陽の寵愛を受けずとも、クントゥルは成長していった。しかし、家の前に生えているグレインの実が隣人のものよりも育ちが悪いように、同じ年頃の子供たちと比べて、クントゥルは少々ひ弱だった。この憐れな子は、今も温かな日差しを身に受ける感覚を知らずにいるのだ。そのため彼の顔はいつも血の気が無く、青白かった。しかし、その目は母親のに似て、星々のように煌めく目だった。彼の父親が当時、その瞳に惹かれ、愚かな選択をしてしまったことには留意しておきたい。 「日光浴が嫌いなイクトミ竜っているのかな?」 ある日、クントゥルはウククにこう尋ねた。ウククはそれに答えず、静かに自分の矢を削っている。目が見えなくなっても彼は凄腕の狩人だ。 クントゥルがこう尋ねるのも無理はない。当時、部族にいる子供たちは誰もが竜の仲間と共に暮らしていた。クントゥルもそれを望んでいたが、暗い場所でずっと過ごしたがるイクトミ竜などいるはずもなかった。イクトミ竜たちは夜に活発になるが、今となれば分かる。彼らにとっても一日中、日差しを浴びないことは受け入れがたいことなのだ。 クントゥルはずいぶんと探し回ったが、日差しを好まないイクトミ竜は見つからなかった。ただ一人、頼れるウククもクントゥルのために獲物を獲って来るばかりで、竜の仲間にはまったく関心が無いようだった。それもまた無理もないことだった。ウククの竜の仲間は、クイールが部族を出ていく時に彼女の助けになると決め、共に荒野へ去っていってしまったからだ。ウククはすっかり竜の仲間がいない日々に慣れてしまっていた。日差しと視力がない日々にも。ウククはクントゥルもいずれ自分と同じように慣れて、尋ねなくなるだろうと思い、一貫して沈黙することでクントゥルに対応していた。 幸いなことに、クントゥルが彼に似ていたのは半分だけだった。でなければ、物語はここで終わっていただろう。 クントゥルはもともと人の言いなりになる性分ではなかった。イクトミ竜の仲間が見つからないことを笑われた時も決して引き下がらなかった。彼を嘲笑した子供たち全員に拳をもってやり返してきた。 最初のうちは、いつもクントゥルの負けだった。背も低く、力も弱いのだから当然である。ボロボロになって地べたに座り込む彼を見て、いじめっ子たちはなおさら気をよくして大笑いした。だが、次第にいじめっ子たちは笑わなくなり、クントゥルをいじめようとすることも無くなっていった。なぜならクントゥルがすぐさま学習し、力を付け始め、竜の仲間がいなくても、力で他人を屈服させられることに気付いたからだ。 やがて大きな嘲笑が、小さなささやきに変わった。しかし、クントゥルは満足できない。大半の子供を屈服させたが、それは表面的なものだった。今でもクントゥルに竜の仲間はおらず、太陽の恩寵も得られていなかった。部族の大人たちから向けられていた冷たさもいくらか薄れてはいたが、それでも彼らの目は嫌いだった。 そのため、クントゥルはなにか立派なことをして自分の凄さを証明することにした。その時にはもう、自分を舐めてかかる者はいなくなり、仲間になってくれる竜も現れるに違いない。 そのチャンスはすぐにやってきた。ある日、みすぼらしい恰好をした老人が部族にやってきて飲み水を求た。部族の者は彼を哀れみ、そのうちの一人は彼を家に招待してこう言った。 「ここにいるのはみな善良な者だ。その様子から察するに遠い場所から来たのだろう。遠慮することはない。どうか我々にもてなさせてくれ。」と。 「お前たちが善良な者だというのなら、最高の料理で儂をもてなせ!儂は腹が空いた!」 老人に言われるがまま、家の主人は最高の料理でこの客人をもてなしたが、七日食べ続けても満足する気配がまったくない。 「なんだ、もう無いのか?ケチケチするな、ぜんぶ持ってこい!」 ここまで来て、家の主人はさすがに客人を家から追い出した。食べ物が尽きたからではない。家の主人は家族や自分自身のことも考えなければならなかったのだ。 「我が家は七日分の食事を提供した。私の善良さならこれで十分証明できただろう。今度は他の者たちの番だ。」 善良とはまったく聞こえのいい言葉で、これを自らを言い表すために使うとなおのこと、気持ちがいいものである。こうして部族の者は、このみすぼらしい老人に様々なものを与えた。だが、誰も彼を満足させることはできなかった。老人の欲望は底知れず、結局は誰もが首を横に振り、手を振って、老人に出て行ってもらうことしかできなかった。 そんな中、クントゥルの家だけは老人を家に招かなかった。 「お前も善良な者であるなら、儂をどのようにもてなしてくれるのか?」 「ハッ、この俺が善良ねぇ。初耳だな。お前に分けてやれるもんなんかねぇよ。あったとしてもやらないがな。お前はもう十分に食って飲んで、いろいろともらっただろう?」 クントゥルが老人を追い出したのを見て、部族の多くの者たちはいずれまた彼を責め立てるだろう。だが意外や意外、この老人はなんとあの悪名高い魔法使いルーミが化けていたのだ。そして彼をもてなしながらも、その胃袋を満たせなかった者は皆、彼の恐ろしい呪いにかかってしまった。彼らが悪夢から目覚めた時には、部族にいた竜たちがすべてルーミに攫われてしまっていたのである! 部族の大半が魔法使いルーミの恐ろしい噂を耳にしているが、彼が竜をさらって何を企んでいるのかは皆目見当がつかなかった。しかし、彼を止めなければロクなことにならないことは分かっていた。竜たちを取り返すため、部族は最も強い戦士三人をルーミに差し向けたが、彼らは誰も帰ってこなかった。 「たとえ実力のある戦士でも、竜の仲間がいなければルーミの相手にすらならないのか…」 部族の者たちが自信を失いかけたその時、クントゥルが立ち上がり、自らを奮い立たせるように「俺が倒す」と言った。そう、彼は「太陽に好かれないクントゥル」!一度も竜の仲間がいなかったやつだ!誰もそんな彼を信頼してはいなかったが、かといって止めることもしなかった。 「これ以上失うものがないことが功を奏したな。少なくとも、持ってもいないものを奪うことはできない。」とクントゥルは考え、自信満々で冒険へと旅立った。 旅の途中でルーミは霧を起こし、クントゥルの行方を阻もうとした。太陽に嫌われているクントゥルが相手なら、日差しが霧を払うことはないと考えたのだ。しかしクントゥルは幼い頃から目の見えない父から狩りと追跡の技術を学んできたため、目が見えなくても、声や気配を頼りに正しい道を見つけることができた。魔法の霧では彼を阻むことはできなかった。 ルーミは次の策を講じた。今度は言葉が話せる三匹のパパッカをクントゥルのところに送り、彼を脅かしたり誘惑させたりしたのだ。この三匹のパパッカは、前に部族が送り出した三人の戦士だった。彼らはそれぞれの弱点によって敗れ、ルーミにこのような姿に変えられてしまっていたのだ。「太陽に好かれないクントゥル」が自分より優秀なはずがないと頑なに信じる三人は、こぞってルーミが自分たちを騙した時の言葉を使い、クントゥルを騙しにかかった。 しかし、クントゥルはそれにも引っかからない。欺瞞と裏切りによって罰された彼の父がいたから、彼も嘘偽りを激しく憎んでいた。そのため彼らの言葉が嘘であるとすぐに見抜けたのだ。一方、嘘を見破られた戦士は恥をかかされたと怒り出し、クントゥルの行く手を阻もうとしていたため、クントゥルも仕方なく力づくで彼らを退けることにした。 こうした数々の試練を乗り越え、クントゥルはようやく魔法使いルーミのもとへ辿り着き、攫われた竜たちを見つけ出した。 魔法使いルーミはクントゥルの肝をつぶしてやろうと、恐ろしい魔法を繰り広げた。しかし空に届くほどの大波でも、灼熱のマグマでも彼を退けることはできなかった。それらは所詮まやかしにすぎず、谷底で以前遭遇した謎の霧のように、まったく取るに足らないものだったのだ。 こうした魔法はクントゥルにはまったく効果がなかったが、攫われた竜は違った。ルーミは魔法で竜たちを使役し始めたが、竜たちもクントゥルの相手ではないことは知る由もない。 「なんて拳だ!今までに見てきたどんな石よりも硬いぞ!」 誰だってそんな拳を食らいたくはない。もちろん、魔法使いルーミとて例外ではなかった。勝ち目がないと知った途端、ルーミは部族から攫ってきた竜など目もくれず、霧に姿を変えて、無様にその場から逃げていった。 まやかしの魔法も嘘偽りの言葉も見破るクントゥルだったが、霧に化けた魔法使いはどうすることもできなかった。しかし、それで諦めるクントゥルではない。彼はとても立派なことを成し遂げて部族全員に自分を証明するべく、どんな手段を使ってでも魔法使いルーミを必ず捕まえると決心した。 その時、彼の目に今も縛り付けられているイクトミ竜が映った。そして、魔法使いルーミが魔法でこいつらを使役できたのなら、自分は力づくで仲間として認めてくれていないイクトミ竜を屈服させればいいのではないか。それでそいつにルーミを追ってもらえば、ヤツの化けの皮を剥がしてくれるはずだと考えた。 彼がイクトミ竜を解放してやると、哀れな竜たちはまだ魔法の影響を受けており、もがいては叫ぶばかりだった。クントゥルも竜たちを落ち着かせるのは一苦労だった。クントゥルはその時に、中でも最も勇敢な一匹を早々に見分けていた。 「さて、こっから俺と一緒に魔法使いルーミを追いかけてもらう。俺の名誉のために…パパッカにされちまった部族の戦士たちのためにもな。」 イクトミ竜はどこか不服なのか、逃げ出そうとするが、クントゥルにバッと押さえつけられ、まったく身動きが取れない。恐れ知らずのクントゥルも、この竜の哀れな眼差しを目にして思わず心を痛めた。このままイクトミ竜を従わせることはできるが、本当にそれでいいか?これでは魔法使いルーミとなんの違いがあるのか?この問いはすぐに解決した。 「お前らの好きな所へ行くがいいさ!」クントゥルが手を放すと、一瞬にしてイクトミ竜は空高く飛んでいき、すぐに空の彼方へ消え去った。 こうしてクントゥルは一人で魔法使いルーミを探すことになった。開放した竜たちは言葉を話せないのだから、共にルーミを捕まえても誰かに見届けられた栄誉にはならない。クントゥルは自分を証明するための第一歩を踏み出したと同時に憂いの一歩を踏み出していた。魔法使いルーミはとっくに霧に姿を変え、どこへ消えていったかも分からない。 クントゥルは以前、部族の語り部と情報通の伝達使から聞いた魔法使いルーミの噂から、ルーミは追跡をかわすために動物に化けるだろうと考えた。そのため、追跡の途中でクビナガライノと力比べをしたり、バッタと睨めっこしたが、なんの成果も得られなかった。やはりイクトミ竜の協力なしに、魔法使いルーミを捕まえることは極めて難しかったのだ。 だが、クントゥルがクイールから受け継いだのは明るい星のような瞳だけではない。クイールが荒野を彷徨い、星の欠片の痕跡を探し求め続けたように、クントゥルも決して魔法使いルーミを捕らえることを諦めなかった。そして部族を旅立った時から、その自信もまったく欠けていなかった。 そしてある日、彼は聞き覚えのある声を耳にした。あれは彼の知っているイクトミ竜だ。彼が解放してやった、部族の中で最も勇敢でありながら、仲間がいないイクトミ竜だ。彼が戻ってきたのだ。その理由は知る由もないが、イクトミ竜は知性溢れる生き物であり、自分に相応しい人物を相棒に選ぶ。きっとクントゥルを仲間として認めたのだろう。だからこそ、こうして舞い戻り、自らクントゥルを導きにやって来たのだ。 クントゥルがイクトミ竜という仲間の協力を得たことで、狡猾な魔法使いルーミもとうとう隠れ蓑を失った。魔法使いルーミはブラウンディアに姿を変え、クントゥルから逃れようとしたが、彼の足はなんと鹿にも負けないほど速かった。 クントゥルに危うく追いつかれそうになったルーミは、クントゥルが泳げないことを知ってか知らずか、とっさにカピバラに姿を変え、勢いよく水の中へと逃げ込んだ。ルーミは心の中でこれで逃げ切れるとほくそ笑んだ。しかし、クントゥルの仲間のイクトミ竜は勇敢なだけではなく、知恵もあった空中で激しく羽をはばたかせ、あっという間にいくつもの竜巻を巻き起こした。風に乗ったクントゥルは足取り軽く、再び追跡を始めた。その速さはまるで足に羽でも生えているかのようで、泳ぎが得意なカピバラの姿をしたルーミに負けることはなかった。 これに驚いたルーミは水を飛び出し、今度は鳥に姿を変え、空に逃げようとした。しかし、これは実に失敗だったと言えよう。以前のクントゥルならここで諦めていただろう。しかし、今の彼には仲間がいる。もはや状況は昔と違うのだ。クントゥルの仲間のイクトミ竜は彼を連れて、空を飛び、雲を抜けて、ついに狡猾な魔法使いに追いついた。逃げられないと悟ったルーミはいっそのこと、と大きな岩に姿を変えた。これならクントゥルとてどうすることもできまいと考えたのだ。しかしクントゥルはその岩をがっしりと掴んだ。「飛べ、相棒!もっと高く!」 彼らはすべての雲を突き抜けるほどまで、ぐんぐん高く飛んでいった。そこでクントゥルは初めて太陽というものを見た。しかし彼が何かを言いかけようとした時、太陽はさらに多くの分厚い雲を呼び寄せて、彼らを取り囲んだ。クントゥルとイクトミ竜は逃げ道を探さねばならなくなり、雷雨や嵐が巻き起こる雲の中を突き抜け、進んだ。だが、高いところというのはとても寒い。クントゥルのまつ毛にも白い霜がついた。魔法使いルーミが化けた岩もカチンコチンに凍ってしまった。これなら、もう何もできないだろう。 こうした数々の危機を乗り越えて、クントゥルとその仲間は部族へと帰り、この奇妙な冒険譚を語った。ルーミが姿を変えたあの岩は、ふさわしい場所に置かれることになった。パパッカにされていた三人の戦士も、ルーミが石になったことで魔法が解け、無事に人間に戻った。彼らは相変わらずクントゥルを避けていたが、それは嫌悪や恐れのためではない。羞恥心と後悔から避けていたのだ。彼らも卑劣な嘘偽りでクントゥルを騙そうとしたのだから。 こうして、クントゥルは部族の者たちに自らを証明し、栄誉を得た。しかし、彼にとって何よりも重要だったのは、ついに自分にイクトミ竜の仲間ができたことだった! |

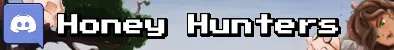



mávuika eu quero ela