
 | Name | 秋暮の炎・3 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 秋暮の炎 | |
| Rarity | ||
| Description | 花翼の集で受け継がれているウォーベン。元々は異なる時代の二つの物語だったようだが、いつの間にか一緒になってしまった。 |
| Table of Content |
| Item Story |
| Obtained From |
| Gallery |
Item Story
| 角を曲がったそこには旗があった。権力を象徴するそれを見た彼は、ほぼ無意識に彼女の手を握る力を強め、熱い興奮を血の中にたぎらせた。それで、彼女の指の隙間から零れ落ちた火種には気づけなかった。次の瞬間、炎が四方八方からごうごうと燃え上がり、倉庫全体を呑み込んでいく。ほの暗く狭い空間は一瞬にして灼熱の窯にも似た墳墓と化した。「急げ、あっちだ!」彼は狼狽えて叫びながらも、彼女の腕を強くひいて、しきりに降り注ぐ火の雨の中から活路を見出そうとしていた。しかし高温が次第に彼の視界をくもらせていく。「無駄よ。」彼女は大人しく腕を引っ張られながら、ささやくように言った。いつもと同じように抗う気配はなかった。「だって逃げ道は私がすべて塞いでしまったもの。」 もはや逃げ出すことは叶わないと察したのか、巨龍は悔恨の混じった雷鳴のような咆哮を上げ、狭く薄暗い洞窟を震わせた。彼女は龍がいたずらに翼を羽ばたかせるのを見ていた。燃え盛る炎を吹き消そうとしているようだ。しかしもう遅かった。獣の絶望が獣自身の抗いを裏切ったのだ。必死にもがく中で液体燃素でいっぱいの燃料缶が壊れ、降りしきる火の雨が龍の血肉を飲み込んでいく。秋の夕暮れに沈むぼんやりとした太陽をも引き裂くかと思わせるほどの黒煙がもうもうと立ちのぼり、岩の隙間から洞窟に差し込むわずかな光すらも遮っていった。 黒煙にむせる彼女は窒息寸前だった。もがきながら彼の傍へと這っていくと、手で彼の顔を探り、不器用ながらも彼の顔を抱いて、お別れに最後のキスを捧げた。「死とてふたりを分かつことはできないわ」と囁き、とうに感覚が無くなっている腕を上げようとした。 しかし、彼女の腕はだらりと落ちた。ずっとギリギリと限界まで引かれていた弓が、張り詰められた狂喜から耳をつんざく甲高い音を立てる。綿のような羽根飾りがついた矢が、まるで稲妻のように秋の夕暮れに吹く涼しい風を裂き、炎に焼かれ悶え苦しみ、のたうち回る巨龍を射った。 灼熱の炎が黄昏の光をも遮ろうとする。その炎の向こうから人々が急いで駆けつけてくるのが彼女の目に映った。彼女は笑みを浮かべ、顔を上げて、上に吊るされた巨龍の頭蓋骨を見ながら、炎が消えた後のことや人々の顔を想像した。 駆けつけてきた人々は花翼の集からの援軍だった。皆、母と共に旅に出た英雄だと彼女には分かった。もうこれで、彼女が何年も追ってきた、この龍にもはや逃げ道など残されていない。 「結局、逃げられなかったわね。」彼女はそう思った。 「…死んでしまった。」エンヤンゴンデホ族親は油のように光る額の汗を拭き、半分ほど焼かれてしまった幕を梁から引きずり下ろすと、傍らへ投げ捨てた。鎮火に駆けつけた仲間たちは族親の周りで、なぜ普段から厳重に管理されている倉庫から火が上がったのか分からず困惑していた。族親は溜息をつき、出火の原因を探して辺りを見回した。しかし、真っ黒に焼け焦げた二つの遺体と族親らの上に吊るされた龍の頭蓋骨の標本——数年前、彼女が一人で討った悪龍——が先ほどと変わらずあるだけだった。倉庫は跡形もなく、焼け落ちてしまった。 |
Obtained From
Shop
| Name |
| n/a |
| items per Page |
|

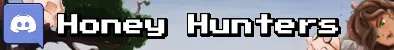



mávuika eu quero ela