
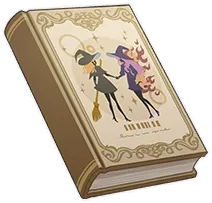 | Name | 小さな魔女と消えない炎·2 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 小さな魔女と消えない炎 | |
| Rarity | ||
| Description | 「もうかなり書いたというのに、ストーリーがまったく進んでおらん。設定ばかりではないか!」「あなたに何が分かるの!それにこれは設定じゃなくて、雑学と知識よ!」 |
Item Story
| 深い森に夜が訪れた。 箒にまたがった小さな魔女の姿が、血緑色の月を横切る。 血緑色は占星学では大きな異変を意味するが、その結果だけで吉凶を判断することはできない。 ——血緑色は本来、この星を支配する種族ニフィリム人の象徴である。神と人の間に生まれた子である彼らの血液は、人間の赤い血と神の金色の血が混ざり合ったような色をしている。しかし実際のところ、緑色の月光は月の構成物質や大地と月との距離、大気等の影響によって生み出されるものだ。 さて、箒に乗って血緑色の月の下を飛んでいた小さな魔女は、「占い師」を名乗る少女に出会った。 「魔女の使い魔になりたいのです。」と少女は言った。 小さな魔女は前からずっと疑問に思っていたことを尋ねた。「占い師って、本当に運命を読めるの?」 占い師はそこで小さな魔女に占いの原理を説明した。読者にも分かるよう、簡単にまとめると…次のような内容だ。 我々の世界では、星象は天上の糸が地上の人々を操る姿を表している。一方他の世界では太陽の黄道エネルギーや、衛星の月のエネルギー、惑星の執政や神々の意志の力、遠き星々の干渉性散乱エネルギー、漆黒宇宙のダークエネルギーを星学の研究対象としている。もちろん我々の星でもそういったものの影響がないとは言い切れないが、巨大な天蓋バリアによりその力がかなり弱まっている。だから他の世界の占星学は、我々の世界よりずっと抽象的だそうだ。 余談だが、他の星では実在の星を「政」、虚構の星を「余」と呼ぶという。小さな魔女がいる星にも、共通する部分がある。 我々も天から下された意思を「執政」と呼ぶ。知的生命体のいる惑星では普通「政」は七つなので、「七政」と呼ぶ。対して虚構の星は一、二、四個と様々だ。小さな魔女のいる星では恐らく一個だろう。空想の星が一個の場合、一般的に「余」は「真っ暗な太陽」であるとされている。 天文学者と占星術師は星本体の天蓋バリア、宇宙、「政」と「余」の比重を計算して、世界とその住民の未来を推理するのが仕事だ。我々の星では天蓋バリアの比重が圧倒的に大きいため、この研究だけでかなり正確な答えが導きだせる。それに対して小さな魔女や占い師のいる世界では、全体を網羅した大きな数式を解く必要があるのだった。 小さな魔女はそれを聞いて、占い師の知識と技術を心の底からすごいと思った。 そこで使い魔の件について、話し合ってみることにした。魔女の使い魔は、魔女と魔力を共有できる。魔力を手に入れれば、占い師はより多くの運命を覗くことができるだろう。けれども、使い魔になれば思いもよらない副作用が現れるかもしれない。どんな結果になるかは、何とも言い切れなかった。 そう、それこそが「血緑色の月」の意味なのだ。大きな異変ではあるが、結果だけを見て吉凶は判断できない——よし、これで横道に逸れずに辻褄を合わせられたな。 「でも残念ながら私は大魔女じゃないの。今はまだ、あなたを使い魔にしてあげられない。」そう小さな魔女は告げた。 「もう一つ魔女と契約を結ぶ方法があります。そっちを試してみるしかなさそうですね。」と少女は答えた。 さて、血緑色の月が輝くこの夜は、ちょうど魔女たちのカーニバルの夜でもあった。 補足すると、カーニバルとは古くから伝わる禁忌の儀式である。魔女たちの魔力はその晩、ピークに達すると言われている。彼女たちは秘密裏に儀式を行い、供物を捧げ、夜を徹してかがり火を燃やし続ける。魔法大陸の西の果てで忘れ去れらたはずの習俗は、何故か深い森の奥で復活していたのだ。そしてこれには普通、大魔女かそれ以上の人物のみが、招待したりされたりできるとされていた。 実際には、カーニバルへの参加は魔女たちの恋愛や結婚事情がダイレクトに関係していたのだが。 …話を戻そう。どうしたことか、占い師は魔女側の事情を理解しているのに、小さな魔女は占い師側の事情を一切知らなかった。とにかく彼女たちはカーニバルに行ってみることにした。まあ、「消えない炎」を見つけられない小さな魔女の焦りを発散するための余興…ということにしておこう。 血緑色の月光の下で、大魔女たちがかがり火を囲んで踊っていた。 小さな魔女と自称「占い師」の少女は重なる雲よりも濃い、かがり火の届かぬ木の陰に身を隠した。 「禁じられた古のカーニバルの夜の翌日、朝日が昇り魔女たちが帰路につく頃を待って——」 「灰の中に残った消えない炎を只人が持ち帰って捧げれば、魔女と契約したものと見なされます。」と少女は語った。 「その方法は必ずうまくいくの?」小さな魔女は尋ねた。 「魔女に拒否される場合もあります…でも魔女は霊媒となるものを格別に愛するものですし、わたしもたとえ恐ろしい怪物になっても構わないと思っていますから。」少女は切実な口調でそう訴えた。 「つまり、それが『消えない炎』ってこと?」小さな魔女の頭の中に、ふと黒い考えが浮かんだ。「じゃあ、その炎を奪えばいいんじゃ…」 血緑色の月明りの下で、大魔女たちは魔女の歌を歌い始めた。 「もしも全てが魔女の歌劇なら、」 「悲しむべき真実など消えてなくなる。」 「我らが祝祭は円満に終わりを迎えた。」 「物語は続く、」 「これからも毎日が、魔女の夜…」 暗闇に潜んだまま、じっと耳を傾けていた小さな魔女は、ちょっと後ろめたい気分になった——それは大魔女や超魔女の中に学校の先生や校長、教頭がいるのではないかと怯えていたからではない——小さな魔女は学校関係者全員を知っていたので、ここには一人もいないことを分かっていた。 ちなみに、小さな魔女の学校にも、緩やかな師弟制度はある。しかしみな年齢が近いため、実質的には年齢で上下関係が決まってしまうところがあった。課外時間には師匠の違う生徒同士の交流も認められており。こうした制度の源流は西の魔女の黎明期にまで遡ることができる。彼女たちは秘伝の呪文や秘儀の交流をタブー視してはいなかった。だからこそ、その時期に西の魔女は勢力を急拡大したのである。この小さな魔女が所属するのも、西の魔女直系の継承者たちのグループであった。別に設定を忘れていて、今慌てて付け足したというわけではないのであしからず。 とにかく物語に戻ろう。彼女は占い師に言った。 「目の前にこんなチャンスがあるんだから、思い切ってやってみなよ!夜が明けたら、その炎を採りに行こう。運悪く怪物になっちゃっても、苦しまないように終わらせてあげるから。」 占い師の少女は、友情の証として、大事にしていた水晶玉を小さな魔女に贈った。 「これは既知のあらゆる運命を喜び、未知のあらゆる悲劇に心を痛める水晶玉です。迷った時は、これに教えを乞うてください。」 この水晶玉の背景はこんなものだ—— |

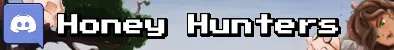



Deviating from Varkas here as well. The Hoyo leaks community is cooked. I guess there'll be less...